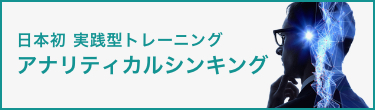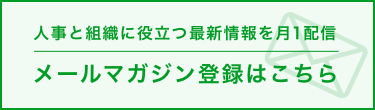コラム
コラム
社員の「愛着と誇り」をどう高める? 日本企業が抱えるエンゲージメントの課題と対策

「エンゲージメント」という言葉は、今やビジネス界では広く知られた概念です。もともとはマーケティングの分野で、自社とクライアントとの深い関係性を示す言葉として使われていたのが、近年ではこの考え方が人事の分野にも応用され、社員と企業の関係性を強化するための重要な指標として注目されています。
社員が会社に対して愛着や誇りを持ち、高い意欲を維持し続けられる会社をつくるためにはどうしたら良いのでしょうか。
エンゲージメントの定義とは。ギャラップ社調査に見る日本の現状と危機感
「エンゲージメント」は、社員が会社や仕事に対して「愛着や誇り」を持ち、高い意欲を維持し続ける状態を指します。 近年、日本企業全体としてこのエンゲージメントが低いことが問題視されています。
米国ギャラップ社による2023年版世界的なエンゲージメント調査では、日本は145カ国中最下位で、「エンゲージしている社員」はわずか5%という結果でした。この状況は翌年も改善せず、日本企業全体としてエンゲージメント向上への取り組みが十分でないことが浮き彫りになっています。こうした現状を受け、エンゲージメント向上に本腰を入れる企業では、まず現場のリアルな声や課題を把握するためにエンゲージメントサーベイを定期的に実施する動きが広がっています。
ギャラップ社の調査項目には、「仕事で期待されていることが明確か」「成長を後押ししてくれる人がいるか」など12項目の質問が設けられています。
例えば、「この1週間のあいだに、よい仕事をしていると褒められたり認められたりした」という質問は、社員が職場で感じる承認欲求やモチベーションに直結します。こうした調査結果から見える課題は、日本企業におけるコミュニケーション不足や評価制度の不備など、多岐にわたります。
| Q01. 私は仕事のうえで、自分が何を期待されているかがわかっている。 Q02. 私は自分がきちんと仕事をするために必要なリソースや設備を持っている。 Q03. 私は仕事をするうえで、自分の最も得意なことをする機会が毎日ある。 Q04. この1週間のあいだに、よい仕事をしていると褒められたり、認められたりした。 Q05. 上司あるいは職場の誰かが、自分をひとりの人間として気づかってくれていると感じる。 Q06. 仕事上で、自分の成長を後押ししてくれる人がいる。 Q07. 仕事上で、自分の意見が取り入れられているように思われる。 Q08. 会社が掲げているミッションや目的は、自分の仕事が重要なものであると感じさせてくれる。 Q09. 私の同僚は、質の高い仕事をするよう真剣に取り組んでいる。 Q10. 仕事上で最高の友人と呼べる人がいる。 Q11. この半年のあいだに、職場の誰かが私の仕事の成長度合いについて話してくれたことがある。 Q12. 私はこの1年のあいだに、仕事上で学び、成長する機会を持った 【ギャラップ公式】たった12問であなたの職場の従業員エンゲージメント状態が分かる(Q12) |
調査結果をどう活かすか?「データ放置」から脱却するために
エンゲージメントサーベイは、社員の愛着や誇りを数値化し、改善すべきポイントを明確にする手段です。しかし、日本では調査結果を正面から受け止めず、データを放置してしまう企業も少なくありません。
例えば、ある製造業の中堅企業では、エンゲージメント調査で「職場環境への満足度」が低いとの結果が出ました。しかし、人事部門は「最近組織再編があったから参考にならない」として結果を棚上げしてしまいました。その後も改善施策は行われず、社員の不満が蓄積し離職率が上昇する事態となりました。
こうした対応は非常にもったいないと言わざるを得ません。調査結果が低かったとしても、それは「伸びしろ」と捉えるべきです。そして、その結果について「なぜそうなったのか」を問い掛け、原因を追求することこそが重要です。
例えば、あるIT企業では「人材育成環境」のスコアが著しく低いとの結果が出ました。当初、人事部門は管理職による部下育成不足が原因だと考えました。しかし、管理職へインタビューを行ったところ、業務負荷が高く育成に時間を割けないという実態が判明しました。この問題に対し、管理職業務内容の整理・改善を行った結果、翌年にはスコアが大幅に向上したという事例があります。具体的には書類作成・管理職同士の会議などで、非効率的な時間の使い方になっている部分があったので、記載内容を簡便にしたり、会議の頻度や時間を減らしたりするなどの取り組みを行うことで、部下と向き合う時間が2割以上増やせるようになったとのことです。
小さな一歩から始めるエンゲージメント向上施策
全社的な大規模施策に取り組むことは理想ですが、それには多大な労力と時間が必要です。そのため、まずは着手しやすい部門単位での取り組みから始めることがおすすめです。
例えば、ある中堅企業ではエンゲージメント調査で「協力体制」のスコアが低いという結果が出ました。そこで部門単位でワークショップを開催し、各メンバーの専門性や役割分担を明示することで相談しやすい環境づくりに取り組みました。その結果、協力体制が改善され、エンゲージメントスコアも向上しました。
また、新しい施策を導入する必要がない場合もあります。例えば、「1on1面談」の仕組みが形骸化している場合、それを改めて活性化させるだけでも効果があります。また既存の年間研修計画内で課題に対応できる場合もあります。このように、小さな工夫や既存リソースの活用から始めることで、大きな成果につながる可能性があります。
エンゲージメント向上への道筋
エンゲージメント向上は一朝一夕で実現できるものではありません。しかし、小さな取り組みでも継続的に行うことで確実に改善していくことができます。そのためには、調査結果を正面から受け止め、「伸びしろ」として前向きに捉える姿勢が重要です。そして、そのデータから原因を深掘りし、具体的な施策へと落とし込むプロセスこそ鍵となります。
日本企業全体としてエンゲージメント率は低い状況ですが、それだけ改善余地も大きいと言えます。「愛着や誇り」を持つ社員を増やし、生産性向上や企業価値向上につなげていくためにも、一歩ずつ着実に取り組んでいきましょう。