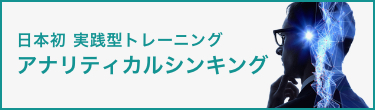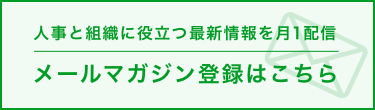コラム
コラム
人材流動化時代を勝ち抜くストック型報酬の威力

人材争奪戦が激化する今、企業の最大の課題は「いかに優秀な人材を確保・定着させるか」です。生産年齢人口の減少と終身雇用の崩壊により到来した「人材流動化時代」。こうした中で優秀な人材を確保するためには、そして採用後も長く定着してもらうためには、社員に「ここで働き続けたい」と思わせる効果的なリテンション対策が欠かせません。そこでカギとなるのが、全社員を対象とした中長期のインセンティブです。今回は、その理由や背景、導入事例などをご紹介します。
報酬制度の崩壊が始まっている
「うちの会社の給与体系、今のままではいけないのでは?」近頃、昇給や給与テーブルについて、こうしたご相談を受ける機会が多くなってきました。全国的な賃上げの流れを受け、多くの企業で等級・役職間の報酬差が縮んだ結果、中には部下の給与が上司を上回る「逆転現象」まで発生するなど、給与体系による歪みに危機感を抱く企業が増えているようです。
また、優秀な新卒人材の獲得競争が年々激しくなる中、ファーストリテイリングを筆頭に、多くの大手企業で初任給30万円以上を打ち出す動きも加速してきています。こうした「初任給インフレ」は既存社員との均衡を崩壊させ、企業の人件費構造に深刻な歪みをもたらしています。これは一時的な現象ではなく、報酬制度の根本的な再構築を迫る構造変化なのです。
中長期間の処遇が再び重要なポイントに
日本の報酬制度は長らく、等級制度をベースとした「基本給+賞与+退職金」の三位一体構造を堅持してきました。しかし、企業が重い負担を続けることが難しくなった結果、この20年で劇的な変化が起きています。
職能給、年齢給、勤続給など年功的な正確を持つ給与体系から、役割給やジョブグレード、ポジションに応じて決定される役割給・成果給主義へ、賞与は生活保障型賞与から業績連動型へ、そして退職金は、終身保障の退職金から自己責任型の確定拠出年金、あるいは退職金制度の廃止へ——。
これらの動きを俯瞰すると、日本企業の報酬哲学は「終身雇用を前提とした生涯にわたる関係性構築」から「短期決済型の契約関係」へと急速に舵を切ってきたことがわかります。しかし皮肉なことに、終身雇用が崩れ、人材の流動性が高まった今こそ、企業と個人をつなぐ「中長期的な絆」が再び重要性を増しているのです。流動的な人材市場では、優秀な人材を獲得するチャンスが増える一方で、そうした人材と長期的な関係を築くことが難しくなっているためです。また、「人的資本経営」という概念の浸透により、自社の人材を資本と捉え、持続的な関係を築くことの重要性が注目されるようになったことも背景として挙げられます。
個人が自身のキャリアを自律的に考えるようになり、加えて、それを支援する転職市場が整備されてきた昨今の雇用環境で優秀な社員の定着を図るには、報酬についても、短期清算型の給与体系だけでは不十分といえるでしょう。こうしたことを背景に、今、再びミドルタイム、ロングタイムでの処遇の整備が重要になってきているのです。
急速に導入が進む、中長期型インセンティブ
人事制度のコンサルティング現場では、MTI(Middle Term Incentive/中期インセンティブ)とLTI(Long Term Incentive/長期インセンティブ)というキーワードが頻繁に飛び交うようになってきました。たとえば、賞与が基本的には1年のパフォーマンスに応じて支給される報酬なのに対して、MTIは3~5年、LTIは5年以上の期間を対象とした報酬制度です。これらは企業価値の向上や利益の拡大に向けたインセンティブ報酬で、具体的な支給形態としてはプロフィットシェア、業績連動ボーナス、ストックオプションなどが挙げられます。
これまでもこうした形の報酬はありましたが、これらの中長期インセンティブは、どちらかと言えば経営陣や一部の幹部社員だけに適用される、特権的な報酬制度でした。しかし今、革新的な企業によって、全社員に対する中長期インセンティブの導入という大胆な動きが出始めてきています。会社の成長と利益を全社的に共有することで、社員と中長期的な関係を築こうというわけです。
全社員が成長パートナーに —クレディセゾンの「ファントムストック」制度
その先駆者とも言えるのが、株式会社クレディセゾン(※)です。同社は2023年より全社員を対象に「ファントムストック」による決算賞与の支給を開始しました。この仕組みでは、経常利益が予算を上回った場合、その超過分の一定割合を決算賞与として、3分の2を現金支給、3分の1を「ファントムストック(仮想株式)」として社員に分配。このファントムストックは2025年の株価で換算されて支給されるため、株価が上昇すれば社員の報酬も増加します。このように積極的な利益還元を行うことにより、社員は単なる「労働者」から「会社の成長パートナー」へと変貌するのです。
※クレディセゾンニュースリリース:全社員を対象とした決算賞与の導入について(PDF)
https://corporate.saisoncard.co.jp/wr_html/news_data/avmqks000000bz57-att/20221125_Release.pdf
人材流動化の時代に、いかに中長期の関係を結び直すことができるか
日本企業は今までの終身雇用の延長で人材を確保してきましたが、この人材流動化時代において、特に中堅・中小企業ではそれも難しくなってきています。事業展開のグローバル化やワークスタイルの変化はもはや不可逆ですから、大企業においても、今のままでは人材の定着はより困難になっていくことが予想されます。
そうした中、優秀な人材を確保するためには、採用だけでなく定着の仕組みづくりを行い、社員と「共に成長し、成功を分かち合う」という新たな関係を構築することが不可欠です。
これらのことから、その仕組みづくりの3本の柱として、以下を提案します。
- 短期・中期・長期の総合的な報酬体系の構築
単年度の成果に対する報酬(短期)、3〜5年の事業成長への貢献(中期)、そして企業価値向上への参画(長期)を組み合わせた立体的な報酬制度を構築すること - 全社員型ストックインセンティブの導入
経営陣だけでなく全社員が会社の成長から恩恵を受ける仕組みを作ることで、「自分ごと」として企業価値向上に取り組む文化を醸成すること - 人的資本経営の本格実践
報酬制度の革新と並行して、エンゲージメント向上、キャリア開発支援(特に育成プログラムの整備と社内キャリアパスの多様化)、ダイバーシティや働き方の多様化の実現など、人材を中心とした経営への転換を加速させること
企業側にとってはシンプルな給与で社員に還元するほど、コスト面でのリスクもまた大きくなってしまいます。ですから、労働者の選択肢が増え、社員と企業がより対等な関係へと移行する今の時代には、いかに流出を防ぐかだけでなく、いかに会社と社員が利益を共有するかという観点が重要なのです。
人材流動化の時代には、優秀な人材がいる企業には多くの人材が集まりやすくなるため、人材確保も二極化が進んでいくと予想されています。人材の確保にお悩みの企業様には、ぜひ中長期的な社員との関係構築を考慮に入れて、報酬戦略や、そのコンセプトを描いてみることをお勧めします。