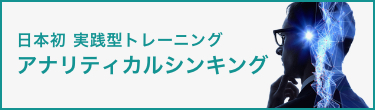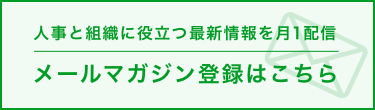コラム
コラム
新卒初任給アップが引き金に?人事制度改革の波

新卒社員の初任給引き上げが、日本企業の人事制度に大きな変革をもたらそうとしています。大学卒の初任給平均額は、東京労働局の発表によると2019年が20万8,000円、2020年から2022年までは21万円(※)とほぼ横ばいでした。しかし、2023年以降、上昇傾向が顕著になり、大手企業を中心に初任給の大幅な引き上げが相次いでいます。この動きは単なる給与アップにとどまらず、人事制度全体の見直しへと波及しつつあります。特に、年功序列型の報酬体系や評価制度のあり方が問われる中で、企業はどのように対応すべきなのでしょうか。今回は、新卒初任給アップを契機とした人事制度改革の現状と展望について詳しく掘り下げます。
(※)都内各公共職業安定所が受理した令和6年3月中学校・高等学校・短大(高専を含む)・大学(大学院)・専修学校卒業者に対する学卒求人の賃金
初任給アップがもたらす衝撃 ~三井住友銀行の例~
新卒社員の賃上げを象徴するニュースとして注目されたのが、株式会社三井住友銀行による大学新卒初任給の大幅引き上げです。同社は2026年4月入行予定の大学新卒者に対し、現行の25万5,000円から30万円へと初任給を引き上げることを発表しました。これは大手銀行としては初めて大卒初任給が30万円台に到達する事例であり、業界内外で大きな話題となりました。
この動きは単なる賃上げに留まりません。同時に、業務領域ごとの専門性や難易度に応じた評価・処遇制度への変更や、入社年次を考慮した階層制度の廃止など、人事制度全体の見直しも進められています。これにより、若手社員への期待値を明確化しつつ、従来型の年功序列的な仕組みから脱却する意図が見え隠れします。
こうした動きはメガバンクだけでなく、大企業から中堅企業へと波及しています。弊社にも「新卒社員の賃上げをきっかけに人事制度全体を見直したい」という相談が増加しており、多くの企業が部分的な改定ではなく、大掛かりな変革を模索しています。
人事制度見直しの背景 人的資本経営へのシフト
人事制度とは、社員の処遇を決定する仕組みであり、「等級制度(職能・職務・役割)」「評価制度(成果、能力、行動)」「報酬制度(基本給・手当・賞与)」という3つの柱から構成されています。この3つを経営方針と連動させて構築することで、社員の納得感やモチベーション向上につながり、それが組織全体の生産性向上にも寄与します。
近年、多くの企業が「人的資本経営」を推進する方針を掲げています。これは、「会社が求める人材像を明確化」し、「人材の見える化」を進めることで、経営戦略と人材戦略を一致させる考え方です。しかし、現行の人事制度がこの方針に適合しないなど、時流の変化を背景に、多くの企業で既存制度への課題感が高まっています。リクルート社調べによれば、61.5%の企業が人事制度や雇用慣行を変える必要性を感じている(※)ようです。
特に問題視されているのは等級や評価基準が曖昧である点です。この曖昧さは「会社としてどんな人材を求めているか」を明確化できない原因となり、人材戦略そのものを阻害しています。こうした背景から、新卒社員の賃上げという報酬制度改革が先行して進む中で、等級・評価基準も含めた人事制度全体の見直しニーズが高まってきたということが現状なのです。
(※)企業の人材マネジメントに関する調査2023 人事制度/人事課題編(PDF)
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20231101_hr_01.pdf
年功序列型報酬体系との決別とジョブ型への移行
新卒社員賃上げは、日本企業特有の「年功序列型報酬体系」の矛盾点を浮き彫りにしました。リクルート社による調査では、多くの企業で職能給(職務遂行能力に基づく給与)が採用されており、管理職では48%、非管理職でも41.3%が職能給による給与体系となっています(※)。しかし、この職能給という給与体系では、職務遂行能力を測る基準として勤続年数が無視出来ない現状もあります。
このような仕組みをそのままに新卒社員のみ給与を引き上げてしまえば、当然、先輩社員の不満や士気低下につながります。日本商工会議所会頭・小林健氏も「初任給を引き上げれば、それ相応に全社員の賃金も引き上げざるを得なくなる」と指摘しています。
そのため、大和ハウス工業など一部企業では、新卒以外も含めた正社員全体で給与水準を見直し、年収ベースで平均10%引き上げる決定を行いました。しかし、一律での賃金アップは企業負担を増加させ、生産性向上や収益改善なしには持続可能性が危ぶまれます。
こうした状況下で注目されているのが、「成果主義」や「ジョブ型」といった新しい報酬体系です。ただし、日本では2000年代初頭にも「ペイ・フォー・パフォーマンス(成果主義の賃金形態)」の導入ブームがありましたが、その結果としてチームワークの悪化や制度の不備によるモチベーション低下、また、賃金格差という新たな概念に馴染めないことによる不満など、多くの弊害も生じました。そのため現在では、「ペイ・フォー・ジョブ(仕事内容に応じた賃金形態)」という考え方への移行が検討されています。
つまり近年のいわゆる「ジョブ型」の人事制度への移行の機運は、成果主義と職能給、双方の課題をクリアするための模索の中で高まってきたわけです。
(※)『企業の給与制度に関する調査2024』
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20241118_work_01.pdf
ハイブリッド型人事制度への期待と課題
ジョブ型人事制度とは、人ではなく「仕事・ポジション」に対して給与を支払う仕組みです。例えば、「東京営業部 渋谷担当 チームリーダー」というポジション自体に対して報酬額を設定し、そのポジションに誰が就いていても同じ給与額とするものです。この仕組みによって、一律での賃金アップというリスクから逃れることが可能になります。
ただ、日本企業では、採用時に応募者本人の潜在的な能力(potential)を評価基準として重視する「ポテンシャル採用」が主流であり、中長期的な育成期間を設けるメンバーシップ型との親和性も高いため、一様にジョブ型へ移行するのは難しいとされています。そのため注目されているのが、「育成期間中はメンバーシップ型、その後ジョブ型へ移行する」というハイブリッド型です。この方式では、新卒採用後3~5年間を目安に様々な部署で経験を積ませ(※)、その後、専門性や役割ごとにジョブ型へ移行します。このモデルは若手社員へのエンゲージメント向上や離職防止効果も期待され、弊社で取り組むコンサルティングでも、多くの企業で導入検討が進んでいます。
しかし、この移行には課題もあります。特に、中堅以上の社員から「若手ばかり優遇されている」という不満が出る可能性があります。長年、年功序列型の報酬体系に慣れていた中堅層からすれば、自分たちは損をしているというように感じられるかもしれません。このような不満への対応として、意識改革や研修プログラム、1on1ミーティングなどによるコミュニケーション強化が必要です。現場のマネージャー任せではなく、会社として意識変革に取り組むことが重要です。
※業務の性質によって期間は異なります
新卒初任給アップという動きは、日本企業全体に大きな影響を及ぼしています。それは単なる給与改定ではなく、人事制度全体への抜本的な見直しにつながっています。時代や経営環境の変化に対応するためには、自社独自の課題や強みを踏まえた柔軟な人事戦略設計が求められます。この機会を活かして、自社に最適な人事制度改革を推進していくことこそ、持続可能な成長への鍵となるでしょう。